
フレーミング効果とは、行動経済学や心理学などで使われる専門用語です。
行動経済学者である、ダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって提唱されました。
今回は、フレーミング効果について、実例や使い方と共に紹介していきます!
YouTubeで、フレーミング効果をアニメーションを使って解説しています。
よろしければご覧ください。
Contents
フレーミング効果とは?

フレーミング効果とは、「問題や質問の提示のされかたによって、選択・選好の結果が変わること」です。
例えば、医者から「この手術を受ければ、90%の確率で助かります」と言われれば安心すると思いますが、「この手術を受けても10%の確率で死にます」と言われてしまうと不安に思ってしまうと思います。
「この手術を受ければ、90%の確率で助かります」も「この手術を受けても10%の確率で死にます」は、どちらも同じことを言っています。
しかし、話のどこに重点を置くかによって、受ける印象が大きく変わります。
フレーミング効果に関する実験
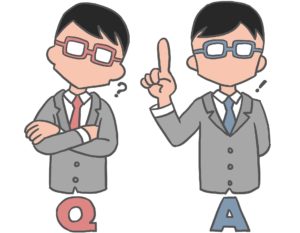
フレーミング効果を調べるために、実際にダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーが行った実験があります。
この実験の被験者は、次のような質問を受けました。
アメリカは、アジア病という伝染病の大流行に備えています。
アジア病の流行を放置してしまうと、死者数が600人に達してしまうと予測されています。
アジア病の対策として、次の2つのプログラムが提案されています。
①A案を採用すると200人が助かります。
②B案を採用すると3分の1の確率で600人が助かりますが、3分の2の確率で1人も助かりません。
あなたはどちらのプログラムを採用しますか?
実際にこの質問に回答した大半の人が①の案を採用したそうです。
内容は同じですが、次のように選択肢が言い換えて質問をした実験もあります。
①a案を採用すると、400人が死にます。
②b案を採用すると、3分の1の確率で全員助かりますが、3分の2の確率で600人が死にます。
このように質問された場合、多くの人が②を採用したそうです。
どちらも同じ内容であるはずなのに、質問を言い換えることで、選択が変わるという結果がでました。
フレーミング効果が起こる原因

フレーミング効果が起こる原因の1つとして、プロスペクト理論が挙げられます。
人は、選択の結果が好ましい場合は、確実な選択を選ぶ傾向があります。
反対に、選択の結果、損失を被りそうな場合は、ギャンブルをしてでも損失を避けようとします。
この傾向があるため、先程の「アジア病」の質問で、最初の質問では①を、選択肢を内容はそのままで言い換えられた質問では、②を選ぶという結果が出ました。
最初の質問では、プログラムを採用した結果、「○○人が助かる」ということに焦点が置かれていたため、多くの人はより確実な選択(A案)を選びました。
しかし、言い換えられた質問では、採用した結果「○○人が死ぬ」ということに焦点が置かれた質問がだったため、回答者はギャンブルをしてでも、損失を避けようとb案を選びました。
フレーミング効果の原因は、プロスペクト理論だけではなく、他の要因も考えられます。
フレーミング効果の使い方

医療
この記事の冒頭でも例に挙げた通り、
「この手術を受けても10%の確率で死にます」と伝えるよりも、「この手術を受けると90%の確率で助かります」と伝えた方が、患者は安心するでしょう。
相手に安心感や好意を持ってもらいたい時には、ポジティブな面を強調した言い方が効果的です!
大きい数字を採用する!
大きい数字を使うことで、消費者を惹きつけることが出来ます。
例えば、電気代が500/月お得によりも、6000円/年お得にと宣伝されていたりなどがあります。
よく栄養ドリンクなどにも、タウリン1グラム配合ではなく、1000mg配合と書かれているのは、フレーミング効果を狙っていると考えられます。
商品の値引き表示
商品の値引き表示には、「○○%引き」と「○○円引き」という2通りの方法があります。
主に、ブランド物や高級品の場合は「○○%引き」、ノーブランドの物や低価格な商品の場合は「○○円引き」という表記の方が良いと考えられています。
無理にでも行動させたいときは損失を強調せよ!
相手に無理にでも行動させたいときは、損失を強調することが効果的だと考えられます。
例えば、がん検診を受ける人を増やしたい場合、「がんが早期に発見されるとリスクを減らすことができます。」と宣伝するよりも、「がんを早期に発見でき
ないと治療が難しくなってしまいます。」と宣伝する方が効果的だと考えられます。
他には、子供に勉強をさせたいときに、試験で80点以上を取れたら1,000円を上げるという、成果報酬型よりも、「先に1,000円を渡すけど、テストで80点とれ
なかったら返してもらい」のように、損失を強調した方が、子供は勉強してくれるようになるかもしれません。
このように、フレーミング効果は受け手にどう感じてもらいたいか、どのように行動してほしいかによって、様々な使い方があります。
今回の内容は以上です。
フレーミング効果は、良くも悪くも、我々の判断に影響を及ぼします。
良い影響であれば、全く問題はありませんが、少なからず悪用する人はいます。
そのような人たちに騙されないようにも、フレーミング効果があることを知っておくことは大切です。
また、宣伝や広告に使う言葉も、フレーミング効果を狙って使うことで、消費者の行動を起こしやすくするため、売り上げを上げることができるかもしれません。
ぜひ、それぞれの使用場面に応じて、フレーミング効果を使ってみてください!
上記以外の本にも、私が実際に読んだ行動経済学の本をまとめて紹介しています!
よろしければ、こちらも参考にして下さい!
-

-
行動経済学のオススメ本13選!入門書~実践本まで徹底紹介!
この記事を読んでくださっている方は、少なからず行動経済学に興味を持たれていると思います。 行動経済学を簡単に表すと、「心理学×経済学」になります。 最近、注目を集めている学問ということも ...
ではでは。