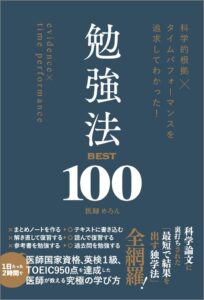
今回は、めろんさん著の『科学的根拠×タイムパフォーマンスを追求してわかった!勉強法BEST100」』を紹介していきます!
皆さんには、資格試験の勉強をしているがうまくいかない、今度の試験は絶対に失敗したくないといった悩みはないでしょうか?
本書はそういった方に役立つ1冊です!
特に社会人の場合は、学生時代と違って、1日に10時間のように、長時間勉強ができるわけではありません。
そのため、限られた時間で、試験に合格するための勉強法が必要になります。
そこで本書では、1日2時間という限られた時間の勉強で、医師国家資格、英検1級、TOEIC900点超えを達成した、医師のめろんさんによって、タイムパフォーマンスと科学的根拠を追求した最強の勉強法がまとめられています!
この記事では、その本書の中から、学習初期にやるべきである、合格体験記を事前に書くことと、日々勉強をする上で意識したい2つの勉強法を紹介していきます!
勉強法BEST100の要約

合格体験記を事前に書く
合格体験記は、普通、合格してから、どのように勉強をしてきたのかを、後になってから書くものです。
しかし、勉強の初期段階で、合格体験記を書くことによって、試験本番で何点取れればいいのか、どの教材をどれくらいのペースで進められばいいのかということを把握することができます。
とはいえ、いきなり0から合格体験記を書くのは難しいと思うので、まずはすでに合格した人の合格体験記を参考にしましょう。
10人、20人以上の合格体験記を読むことによって、合格までにはどんな教材を使う必要があるのか、どれくらいの勉強量が必要なのか、1日にどれくらいこなしていけばいいのかといった情報を集めていきます。
そして、自分の目標の目標を達成するためには、どうやって勉強をすればいいのか、合格体験記を事前に書くことで、考えていきます。
そこで、この合格体験記を書くためには、最終的に達成したい目標と、勉強計画を立てる必要があるので、この2つを設定する際のポイントを本書をもとに紹介していきます。
まず、効果的な目標を立てる際には、具体化、数値化した上で、期限を決めるようにしましょう。
「英語ができるようになる」といった、漠然とした目標では、どの程度までいけば達成したことになるのかわかりません。
またゴールが明確でないので、その後の勉強計画も立てることが難しくなってしまいます。
そのため、TOEICで900点を取る、TOFLEで70点を取るといったように、明確な目標を立てるようにしましょう。
さらに、目標は明確にするだけでなく、必ず締め切りも設定することが大切です。
人は、締め切りを設定すると、その作業や目標に向かって効率的に行動を進めるようになる傾向があります。
そのため、目標は明確にすることと、締め切りを設定することの2つを意識して、立てていきましょう。
ここで立てる目標は、最終的なゴールである長期目標になります。
続いて、勉強計画を立てる際には、その長期目標から逆算して、中期目標を指定し、それを踏まえて短期目標を設定していきましょう。
その長期目標を達成するためには、何をしなければいけないのかを考え、3ヶ月後や半年後などに、どの参考書をどれくらい終わらせる必要なあるのか、中期目標を考えていきます。
そして、その中期目標を達成するために、1ヶ月後にはどれくらい進めればいいのか、短期目標を考え、最終的に、毎日のノルマに落とし込んでいきます。
私が現在勉強している、CCNAという資格試験をもとに、次のように、目標設定を立ててみました。
長期目標:2025年10月にCCNAを合格する(この記事の作成時から6ヶ月後)
中期目標:3ヶ月後までにPing-T(教材)を3周する
短期目標:1ヶ月後までにPing-Tを1周する
毎日のノルマ:毎日50問ずつ問題を解く
このように、長期目標を立てたら、そこから逆算して、勉強計画を立ててみてください。
そして、勉強を成功させるためには、長期目標と短期目標のバランスが大切です。
具体的には、長期目標は高く、短期目標は低く設定するようにしましょう。
短期目標がきびしいものだと、毎日のノルマも大変になってしまいます。
勉強を始めたての時は、モチベーションが高く、その勢いで計画を立ててしまうと、現実的ではない計画になってしまうことが多々あります。
その結果、毎日のノルマを達成できない日々が続いてしまい、どんどんモチベーションも下がり、最終的に勉強をやらなくなってしまうのです。
そのため、短期目標は、実現できる範囲で低く設定することが大切です。
以上のポイントを意識して、目標と勉強計画を立てて、勉強の初期段階で合格体験記を書いてみてください!
続いては、実際に勉強を進める上でのポイントを紹介していきます。
勉強は書かずに読め!
中には、「自分は書いた方が覚えられる」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、書いて覚える勉強は、とても非効率的な勉強なのです。
本書でも、書く勉強は、黙読や音読の3倍以上の時間と労力がかかると書かれています。
3倍以上の時間と労力がかかっても、それを上回るほど、記憶に定着率がいいのであれば、問題はありませんが、残念ながら、書いて覚えても、人はすぐに忘れてしまいます。
忘れてしまうからこそ、定期的に復習が必要なのですが、書いて勉強をしていては、勉強に時間がかかり過ぎてしまい、復習に充てる時間を確保することが難しくなってしまいます。
また特に社会人の場合は、普段仕事や家事をしながらの勉強になるため、いかに短い時間で、効率よく覚えることができるかということが重要なポイントになります。
そのため、書いて読んで覚える勉強よりも、読んで覚える勉強を中心に進めていきましょう。
そして、読んで勉強をする時には、黙読よりも、音読の方が記憶に残りやすいです。
音読は、視覚的に情報を読みながら、声に出すことで聴覚も刺激することができます。
さらに発話により運動感覚も加わるため、複数の感覚を同時に使いながら勉強をすることができ、脳が活性化されるので、記憶により定着されやすくなるのです。
もし電車の中など、声を出して勉強をするのが難しいという場合は、口パクでも効果があると言われています。
実際に私も学生時代にTOEICの勉強をしていた時は、電車の中ではマスクをつけて、口パクで単語を発音したり、英文の音読をしていました。
そのため、勉強は書くよりも読む、黙読よりも音読を優先して取り入れるようにしてみてください!
復習をやらない人は成功しない
みなさんは、復習の時間を設けているでしょうか?
もし日々の勉強で復習の時間を設けていないのであれば、今すぐに復習を取り入れるようにしてください。
残念ながら、一部の天才を除いて、一度解いたり、読んだりしただけでは、時間が経つとともに忘れていってしまいます。
そこで復習をすることで、忘れていってしまうことを防ぎ、長期記憶に定着させていくことが大切なのです。
逆に復習をしないで勉強をすることは、穴の空いたバケツに水を入れ続けているようなもので、時間も労力も無駄にしてしまいます。
そこで効果的に復習をするためには、間隔をあけた反復学習を行いましょう。
学習者1000人を対象に、単語やフレーズを学習させた研究では、一度にまとめて学習する集中学習のグループと、間隔をあけて学習をする分散学習のグループにわけた研究では、分散学習をしたグループの方が、短期記憶と長期記憶の両方で優れていたという結果が出ました。
そのため、復習といっても、学んだ後にすぐ振り返るよりも、ある程度間隔をあけてから行った方が、記憶の定着には効果があるのです。
では、どのように復習の計画を立てればいいのか?
著者は、次のやり方で復習をしていたと本書で書かれています。
序盤:1日前と2日前の復習を行う
中盤:当日分の新しい範囲の学習をする
終盤:当日分の復習をする
『勉強法BEST100』より
このサイクルで勉強を進めていくことで、当日、次の日、またその次の日と、1度学んだ範囲を3日連続で復習することができます。
もちろん、復習をするためには、ある程度の勉強時間を確保する必要があります。
そのため、著者のサイクルでは負荷が大きすぎるという場合は、前日と当日分のみ復習をする、確信を持って正解できた部分は飛ばすなどして、負荷を調整してみてください。
また復習を行う際には、問題集を順番通りに解き直すのではなく、ランダムに復習をする方が効果的です。
ページ順に復習をしていると、どうしても答えを暗記してしまい、肝心な解答の根拠を覚えていないなんてことになってしまいます。
そのため、ランダムに復習をすることが大切です。
また、ランダムに復習することの効果は、実際の研究でも、記憶の識別力や応用力、学習の効率と記憶の保持率が上がることがわかっています。
最近では、アプリ版の教材では、指定した範囲の問題をランダムに出題してくれるものもあるので、そういったものをうまく活用してみてください。
また紙の参考書の場合も、偶数番号だけとく、3つ飛ばしで解くといったようにすることで、ランダム復習を実践することができます。
そのため、ある程度間隔をあけて復習をすることと、ランダムに復習をすることを、ぜひ意識して、日々の勉強に取り組んでみてください!
本書では、この記事では紹介しきれていない、科学的に根拠に基づいた、タイムパフォーマンスの高い勉強法がまだまだ紹介されています。
そのため、これまで試験勉強がうまくいかなかったという方や、今度の試験勉強は成功させたいという方は、ぜひ本書を読んでみてください!
『科学的根拠×タイムパフォーマンスを追求してわかった!勉強法BEST100」』の購入はこちらから!
ではでは。