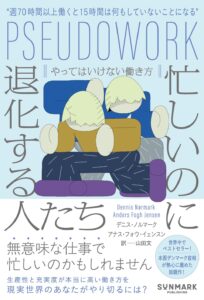
今回は、デニス・ノルマーク氏、アナス・フォウ・イェンスン氏著の『忙しいのに退化する人たち』を紹介していきます!
皆さんには、毎日忙しい割に成長していない、今の仕事の忙しさから脱却したいといった悩みはないでしょうか?
本書はそういった方に役立つ1冊です。
本書は、デンマークでベストセラーとなり、デンマークの首相が熱心に薦め、国民の100人に1人が勝ったという、異例の1冊です!
そんな本書では、人類学者のデニス氏と、哲学者のアナス氏によって、なぜ現代人は忙しい割に成長できていないのか、また労働時間は減らないのか?について書かれています。
この記事では、その本書の中から、労働は週15時間になるはずだった!?偽仕事が労働時間の減少を阻んでいる、偽仕事が生まれる理由と解消法の3つについて紹介していきます!
忙しいのに退化する人たちの要約

労働は週15時間になるはずだった!?
過去には、技術の発展により、人間の労働時間は減っていくはずだと考えられていました。
20世紀初めから半ばにかけて、経済学者、政治家、社会学者は、未来の社会は長い休暇の社会になると予想していました。
また、19世紀にはベンジャミンフランクリンが、1日4時間の労働で事足りると論じていました。
そして、経済学者のケインズは、2030年には平均労働時間は週15時間になると予想していました。
そのため、労働時間の長さよりも、自由な時間をどのように使うかということが真の課題だと考えられていたのです。
では、今の私たちにとって、そんな夢のような話は実現したのか?
統計によると、日本人の平均労働時間は、平均で週42時間、男性の場合は46時間という結果が出ています。
他の国でも、労働時間は平均で週40時間前後となっています。
イギリスで起こった産業革命後、労働時間は増え、1850年代のイギリスの産業界では、週の労働時間が70時間になったことを考えると、労働時間は減ったと考えられます。
現代社会において重要な発明の多くはこの時期に生まれ、人は身をこなして働いていました。
ですが、当時の人々は、発明により、将来はもっと自由な時間が増えるはずだと希望を抱いていたのです。
そして実際に、1900年代後半にかけて、労働時間は徐々に減っていきました。
デンマークの鉄鋼業では、1990年は週60時間もあった労働時間が、1915年には週56時間、1958年には週48時間、1967年には週40時間、そして1990年には週37時間へと減っていたのです。
他の欧米諸国でも、似たように、労働時間の減少は起こりましたが、1990年以降は、さらに労働時間が減少することはありませんでした。
むしろ、アメリカでは1980年に、100年ぶりに週あたりの労働時間が増えたのです。
日本はどうだったかというと、厚生労働省の「わが国の過去50年間(1973~2023年)の労働時間の推移についての考察1」によると、1973年以降、1990年にかけて週あたりの平均労働時間は50時間以上となっており、その後現在にかけて徐々に減っていますが、週40時間あたりからは、減少することはありません。
他の国でも同じように、ケインズが予想していたような、週あたりの労働時間が15時間になるという社会は実現していません。
では、これほど、テクノロジーが進化し、様々なものが便利になった世の中で、なぜ私たちの労働時間は減らないのか?
むしろ、労働時間が増える現象が起こっているのはなぜなのか?
続いては、労働時間の減少を阻んでいる、偽仕事について紹介していきます。
偽仕事が労働時間の減少を阻んでいる
2009年にスウェーデンの民間航空局が、7名の職員を解雇したということがありました。
その理由は、就業時間の最大75%をインターネットを使って、ポルノサイトの閲覧にあてていたからです。
そんなことをしていれば、解雇されて当たり前だろうと思われるかもしれませんが、就業時間に仕事とは関係のないサイトを閲覧している事例は、スウェーデンの民間航空局に限った話ではなく、全世界中に広まっています。
実際に、スパイウェアという会社が開発した、オンライン活動を監視するためのツールによると、ポルノサイトへの全通信の70%が、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時の間に行われているという結果が出ました。
さらに、明らかに個人で使用する商品の売買が勤務時間中に多く行われ、夜間帯や週末には減少するということが起こっています。
またアメリカで行われた調査によると、人々は週に平均して8.3時間を仕事とは無関係のサイトで過ごしているという結果も出ています。
正直、私にも心当たりはありますが、おそらく皆さんにも心当たりがあると思います。
私の会社では、別の部署で、会社支給のPCでネットフリックスを勤務中に見ていたことが指摘されていましたが、皆さんの会社でも同じようなことがあるのではないでしょうか?
労働時間は減少していないわけですが、実際には全就業時間、仕事に集中できているわけではなく、仕事には関係のないことをしている時間もあるのです。
もちろん、中には仕事をしている時間もありますし、忙しくしている人もいます。
しかし、問題は、どんな仕事をしているのかということです。
取り組んでいる仕事の中には、みんな「意味のないこと」だとわかっているものや、誰もろくに目を通さない報告書の作成、無駄な会議など、無意味なものもたくさんあると思います。
本書では、こういったなくても何の支障のない仕事や、忙しいふりをするために、でっちあげる仕事など、様々な種類の無意味な仕事をまとめて、偽仕事と表現しています
また、私たちの労働時間が減らず、週15時間の労働が実現しないのは、この偽仕事が原因なのではないかと書かれています。
そして、この偽仕事が増えるようになったのは、人類の労働が、農業から工業、オフィスへと至る道のるで起こりました。
農業や工場での仕事は、ほとんどが目に見える仕事です。
そして、労働者がちゃんとやっているか、管理者によって、監視されていました。
しかし、オフィスワークが台頭してきてから、周りからは、ハッキリと見えずらい仕事が増えました。
オフィスワークでは、農業と工場のように、労働者が何をしているのか、また仕事の進捗を正確に把握することは難しいのです。
このような、舞台裏の仕事が増えたことによって、偽仕事の温床が出来上がったのです。
もちろん、中には偽仕事ではなく、本当に意味のある仕事もあると思います。
しかし、全部の仕事が意味のあるものというわけではなく、中には意味のないものや、よく考えると、無駄な仕事もあるのが事実なのではないでしょうか?
では、なぜ意味のない偽仕事が生まれ、労働者は、偽仕事に時間を使うようになったのか?
本書では、偽仕事が生まれる理由や背景とその解決策が解説されていますが、この記事の続きでは、そのうち2つを厳選して紹介していきます。
偽仕事が生まれる理由と解決策
偽仕事の解決策の1つ目が忙しさ崇拝からの脱却です。
かつては、自由時間が名誉の印とみなされており、懸命に働かなければいけない人は、見下されていました。
しかし、今では、仕事から名誉が生まれると考えられており、忙しさが一種のステータスになっています。
忙しいということは、自分は会社に求められているのであり、価値のある人材ということだと考え、逆に仕事がなく、忙しくないと、自分には価値がないと考えてしまうのです。
最近では減ってきましたが、日本でも仕事を定時で上がる人はやる気のない人で、たくさん残業している人が、頑張っている人だとみなされる風潮がありました。
今では以前のように、定時で帰るとやる気がないとはみなされなくなってきていると思いますが、今でも、忙しいことがいいことであると考えられています。
そして、忙しくするために、無駄な予定を入れたり、忙しいふりをして仕事を選ぶ、仕事がない時期は、何かやることを捻出して忙しくするというように、偽仕事を増やしていくのです。
さらに、周りが定時でも帰らないと、仕事が終わっていても、先に帰りづらく、周りに合わせて、無意味な仕事をしながら、オフィスで時間を過ごすのです。
このように、忙しいことがいいことだという考えに陥ってしまっていると、本来はもっと早く帰れるはずなのに、自ら無駄に仕事を増やしてしまい、労働時間が減らなくなってしまうのです。
だからこそ、偽仕事を減らすためには、忙しさ崇拝から脱却する必要があるのです。
では続いて、2つ目の偽仕事の解決策が、解決策を捻り出すことをやめることです。
偽仕事は悪意だけで生まれるわけではなく、善意によっても生まれます。
皆さんの職場でも、何か新しいシステムを導入した結果、無駄に仕事が増えたということはないでしょうか?
システムを導入することを決めた側は決して悪意があったわけではなく、むしろもっと仕事がやりやすくなるように、善意で導入を決めたかもしれません。
しかし結果的に、システムの導入が新しい仕事を生むことにつながれば、偽仕事が生まれ、無駄な仕事が増えるのです。
また、そのシステムを導入するにあたって、裏では何度も会議や話し合い、情報収集と行ったことが行われていたはずであり、そうった時間も、結果的には偽仕事になってしまうのです。
何か、今の組織構造を変えたり、新たな方針を立てたり、システムを導入したりなど、何か現状を変えなくては、新しいものを導入しなくてはという思いに駆られるかもしれません。
しかし、たいていの場合は、最初にあったものよりも、あまり効果が変わらないものであることが多いのです。
私の会社でも、社員のウェルビーングを向上させようという取り組みがあり、その一環として、毎月自分のウェルビーングを測定するアンケートが実施されるようになりました。
会社としては、社員のウェルビーングを把握して、何か問題があれば、対処したいという意向があるのかもしれません。
しかし、実際には多くの人が、毎月アンケートに答えることを億劫に感じており、ストレスになっており、みんな当たり障りのない結果が出るように回答しているのです。
まさに、ウェルビーングのアンケートは偽仕事と呼べるものであり、何も生み出すことがないのに、毎月やらなければいけない仕事になってしまっているのです。
もしかしたら、皆さんの職場では、私の会社の事例よりも、もっと負荷の大きい偽仕事が生まれているかもしれません。
こういった事態を防ぐためには、常に何か改良をしようとするのではなく、その解決策が、そこから生まれる恩恵を台無しにしないかを考えることが大切です。
そして、その解決策によって、消される仕事よりも、生まれる仕事が多いのであれば、すぐに中止するべきなのです。
また、それほど大きい問題ではないのであれば、解決策よりも、問題の方を大目に見るという、妥協が大切になるのです。
本書では、偽仕事への解決策がまだまだ紹介されておりますので、興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください!
本書では、この記事では紹介しきれていない、私たちの職場に蔓延る偽仕事や、その解決策、偽仕事に対処するために、個人やリーダーにできることは何かといった、様々なことが書かれています。
そのため、今の自分の仕事では、偽仕事によって、多くの時間が無駄になってしまっているなと感じる方は、ぜひ本書を読んでみてください!
『忙しいのに退化する人たち』の購入はこちらから!
ではでは。