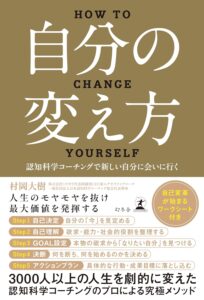
今回は、村岡大樹さん著の『自分の変え方』を紹介していきます!
皆さんには、今の自分を変えたいけど、なかなか行動に移せない、毎日やりたくない仕事をしているけど、何を自分がしたいのかわからないといった悩みはないでしょうか?
本書はそういった方に役立つ1冊です。
勉強や仕事、プライベートなど、様々な場面で、今の自分を変えたい、もっとこうなりたいという理想があると思います。
しかし、今の自分を変えることは簡単なことではなく、多くの人が途中で挫折してしまいます。
そこで本書では、2016年からコーチングを始め、ご自身で代表取締役CEOを務められている株式会社ミズカラでは、5000人以上にコーチングを提供してきた、認知科学コーチングのプロである著者によって、自分の変え方が解説されています。
この記事では、その本書の中から、なぜあなたは変わることができないのか?私たちは無意識によって動いている、自分を変える5ステップの3つについて紹介していきます!
自分の変え方の要約

なぜあなたは変わることができないのか?
今の自分を変えようとしたが、変えられなかった方の中には、「自分は怠け者だから変われない」と、自分の責めてしまっている方もいるかもしれません。
私も過去にダイエットに失敗した時は、「自分はどうせ運動を続けられないから痩せられないんだ」と自己嫌悪に陥ってしまったことがあります。
一方で、世の中には、自分の目標に向かって猛烈に進み、どんどんとなりたい自分を実現している人たちがいます。
では、自分を変えられる人は、特別な才能を持っていて、自分を変えられない人には、その才能がないのか?
実は、自分を変えることができるかは、才能では決まりません。
そもそも、自分を変えたくても変えることができないのは、当然のことなのです。
それは、人間には変わりたくないという本能が備わっているからです。
この本能の働きは、ホメオスタシス(生体恒常性)と呼ばれています。
ホメオスタシスの代表的な例として挙げられるのが、体温調節です。
私たちの体は、暑いと汗を出して体温を下げようとし、寒いと体の外に熱を出さないようにして体温を保つことで、自分にとって快適な体温に調節しようとします。
他にも、ホメオスタシスが正常に機能していることで、血糖値や血液量、生理機能など、身体の様々な機能が正常に保たれており、私たちは快適な領域であるコンフォートゾーンにとどまることができるのです。
このホメオスタシスは、私たち人間祖先が過酷な環境を生き残るためには、効果的な機能でした。
しかし、現代においては、マイナスに働いてしまうこともあります。
それが、何か新しいことに挑戦するときや、今の自分を変えるときです。
人は急に大きく変わってしまうと、慌てて自分がもとにいたコンフォートゾーンに戻ろうとしてしまいます。
そのため、何か新しいことを始めて、生活リズムや環境がガラリと変わると、その急激な変化についていくことができず、元の生活や行動に戻ろうとしてしまうのです。
そのため、今の自分を変えたくても、最初は行動できても、続かなかったり、途中でやめてしまうということになってしまいます。
また、継続ができない人は、よくモチベーションが上がらない、保てないという話をしますが、本書では多くの人はモチベーションの言葉の意味を間違ったまま使っていると書かれています。
モチベーションとは、自分の目標実現のために、苦しいことでも乗り切るためのエネルギーのようなイメージがあるかもしれません。
しかし、モチベーションの本来の意味は、コンフォートゾーンに戻ろうとする力を指しているのです。
これを聞いた方の中には、「目標を実現できたり、自分を変えられるのは、モチベーションが高いからじゃないの?」と終われる方が多くいると思います。
目標を実現したり、自分を変える人にとってのコンフォートゾーンとは、現状の自分ではありません。
目標を実現した姿や、なりたい自分になった姿がコンフォートゾーンになっているのです。
だからこそ、コンフォートゾーンからはズレている現状の自分に気持ち悪さを感じ、コンフォートゾーンに戻ろうと、行動を起こすことができているのです。
ということは、目標やなりたい自分をコンフォートゾーンにすることができれば、誰でも自分を変えることができるのです。
では、どうすれば目標やなりたい自分をコンフォートゾーンにすることができるのか?
今の自分の世界の外側にゴールを設定して、現状よりも、そのゴール世界の方にリアリティを感じることによって、実現することができます。
今の自分を変えるためには、当然ですが、これまでと同じようなことをやっていてはかわることができません。
そのため、今の自分の世界の外側にゴールを作ってあげることが大切です。
ちなみに私は最近テニスを始めたのですが、目標をラリーができるようになる、サーブが入れられるといった、やっていればいつか達成できるものではなく、テニス歴が3年近くある知り合いに試合で勝つという目標にしました。
そして、頭の中で、その知り合いにテニスの試合で勝つシーンを何度も何度も繰り返し、想像していたのです。
それまでダイエットに失敗してきて、太っていた私にとっては、テニス経験者にテニスで勝つというのは、まさに外に世界のゴールでしたが、それを設定したことによって、普段の生活が変わり、体型も変わり、今ではテニスを始める前とは別人になることができています。
実際にテニスを始めて、痩せるために筋トレを始めてから、半年くらいが経ちますが、体重は10キロ近く落とすことができています。
そして、たまにではありますが、テニスの試合では、その知り合いに勝つことができるときもあります。
これまでダイエットに失敗してきたのに、今回は続けることができているのは、その知り合いにテニスの試合で勝つことを何度も何度も頭の中で想像したからだと思います。
そのため、テニスの試合に勝つことの方が、試合で負けることよりも、リアリティを感じていたのだと思います。
その影響で、私にとって、試合に勝つことがコンフォートゾーンになっており、そのために運動をすることが当たり前になっていったのです。
私がこの目標を立てて、テニスや筋トレに取り組んだのは、本書を読む前だったので、厳密にはやり方は違っています。
しかし、それでも今の自分を変えるためには、今の自分の外の世界にゴールを設定すること、設定した世界にリアリティを感じることは、とても大切な要素だと思いました。
では続いては、今の自分を変えるために、もう一つ重要な要素である無意識について紹介していきます。
私たちは無意識によって動いている
既にご存知の方も多いかもしれませんが 、私たちの行動の多くは、無意識によって行われていると言われています。
私たちの脳は消費エネルギーを抑えるために、無意識を活用しており、実に95%の意志決定が無意識に行われていると言われています。
そして、この無意識の中には、信念が存在しています。
信念とは、自分でも気づかずに信じているものや、価値観といったもので、日々の意思決定に大きな影響を及ぼします。
それは、私たちの脳が信じていることを実現するために働いているからです。
今の自分を変えようとせずに、現状を維持することがゴールになってしまっていると、無意識はそれに対して、物事の重要度を定めていきます。
そのため、目の前に自分を変えるチャンスがあったとしても、それに気づくことなく、いつも通りの生活を続けてしまうのです。
このように、無意識によって、行動や選択が行われることにより、今の自分という結果が生み出されているのです。
そして、無意識には、生まれながらに持っている先天的な無意識と、外の世界の人たちとの関わりの中で形成される後天的な無意識の2種類があります。
人によって、性格や気質が異なるように、生まれながら持っている無意識は人によって違うのです。
さらに、生まれてから成長していく過程で、いろんな人と関わる中で、後天的に作られていく無意識があります。
2つの無意識が組み合わさった総合的な無意識によって、私たちの選択と行動の大部分が決定されてきています。
だからこそ、今の自分を変えたいなら、自分の人生を創っているとも言える、無意識を理解する必要があります。
そして、自分の今の無意識を理解して、それを自分を変えるために書き換えてあげることで、日々の選択と行動が変わり、人生を変えることができるのです。
では、最後にその自分を変えるための5つのステップの概要について紹介していきます。
自分を変える5ステップ
著者が行なっている認知科学によるコーチングでは、1回1時間のセッションを、6〜12回、3ヶ月〜1年にかけて行います。
その認知科学コーチングは、大きく次の5つのステップで構成されています。
①自己決定
②自己理解
③GOAL設定
④決断
⑤アクションプラン
『自分の変え方』より
本書では、それぞれのステップごとに、どういったことをコーチングで行っているのか、またワークが用意されています。
この記事では、そのワークを紹介することはできませんが、それぞれのステップでどういったことをするのかを紹介していきます。
まずステップ1の自己決定では、今のままの生き方でいくのか、今の生き方の外側にいくのかを決めていきます。
今の自分を変えるためには、それ相応の覚悟が必要です。
そのため、まずは今の生き方の外側にいくという決心をして、なぜ今の自分から変わりたいのか、どうなりたいのかということを考えていきます。
続いて ステップ2の自己理解は、自分が無意識に信じている通りの世界を創っていることと、自分が何者であるかに気づくためのステップです。
先ほども紹介したように、私たちの意志決定の大部分は無意識によって行われています。
そのため、自分を理解するためには、自分の人生を創っている無意識を理解する必要があるのです。
そして、自分が何者かということを理解することで、自己理解を深めていきます。
自分が何者かを理解するためには、次の3つの切り口で考えていきます。
①自己欲求:無意識の中にある欲求、誰かに止められても思わずやってしまうこと
②自己能力:動作・行動の勝ちパターン、得意なこと
③自己機能:世の中から「〜屋さん」と認識されているか(お金をもらえるレベルで社会に貢献していること)
『自分の変え方』より
本書で用意されているワークを活用して、自己理解を深めることで、本来の自分を元に、GOALを設定することができます。
またこの3つの切り口を考えることによって、自分ならできる気がするという、自己効力感を高めることができるのです。
続いて、ステップ3ではGOALを設定していきます。
GOALは、ステップ2の自己理解を元に、どんな自分になりたいのか、どんなことで力を発揮したいのかを考え、GOALを設定していきます。
また、先ほども紹介したように、自分を変えるためには、今の自分の世界の外側にGOALを設定する必要があります。
そして、この時に大切なのが、ゴールを達成できるかどうかを気にしないことです。
達成できるかどうかを気にし過ぎてしまうと、自分の世界の外側にGOALを設定することができなくなってしまいます。
本当に大切なことは、達成できるかどうかではなく、自分が変わらないとたどり着けない高いゴールに最後まで執着し切ることなのです。
また、そのゴールがあなたの自己欲求に根ざしているかどうかも大切です。
他人軸や世の中で良いとされていることでは、本当のあなたが望んでいる姿ではありません。
そのため、ステップ2で考えた自己理解を元に、自己欲求に根ざしたGOALを考える必要があります。
そして、ステップ4の決断では、何を断ち、何をやると決めるのかを考えます。
今までの自分にとってのコンフォートゾーンから抜け出すためには、今までの自分がやっている選択や行動とは、違うことをしなくてはいけません。
私の場合は、知り合いにテニスで勝つと決めてから、お酒を飲むことをやめて、筋トレや運動の時間を増やすようにしました。
お酒は付き合いで飲むことは少しありますが、以前は週6〜7日と毎日のように飲んでいたのが、今では多くても週に1回になっています。
そして、以前の自分ではありえなかったのですが、週に5〜6日は筋トレかテニスをするようになっています。
ぜひ皆さんも、今の自分を変えるためには、何をやめて、何をするのかを考えてみてください。
そして、最後のステップ5、アクションプランでは、いつからどんな行動を開始するのか?いつまでにその行動を完了させるのか?その行動を通じてどんな成果を獲得したいのか?といったことを具体的に決めていきます。
何をするのか決断だけしても、行動に移せなければ意味がありません。
そのため、自分を変えるためには、どんなことをいつまでにするのか、アクションプランを考えて、行動に移すことが大切です。
このアクションプランを考える際には、そのプランがコントロール可能である、測定可能であるという2つの条件を満たしているかも考えてみてください。
以上が、認知科学コーチングによる、自分を変えるための5ステップです。
本書では、実際に使われているワークも合わせて紹介されているので、ご自身でも実践することができるようになっています。
そのため、自分を変えたいという方は、ぜひ参考にしてみてください!
本書では、この記事では紹介しきれていない、今の自分を変えるために役立つことが、まだまだ書かれています。
そのため、今の自分を変えたいけど、なかなか実行に移せないという方は、ぜひ本書を読んでみてください!
『自分の変え方』の購入はこちらから!
ではでは。