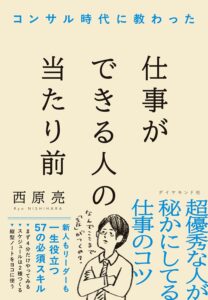
今回は、西原亮さん著の『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』を紹介していきます。
皆さんには、頑張っているつもりなのに評価されない、周りと比べて仕事ができないといった悩みはないでしょうか?
本書はそういった方に役立つ1冊です!
本書では、仕事ができる人になる唯一の条件は、周りから信頼されることであると書かれています。
そして、信頼を得るためには、当たり前のことを当たり前のようにやる必要があるのです。
では、仕事ができる人は、どんなことを当たり前にやっているのか?
にっしー社長として、YoutubeやTick Tokでご活躍されている著者が、コンサル時代に超優秀名先輩から叩き込まれた、仕事ができる人が当たり前にやっていることが本書でまとめられています!
この記事では、その本書の中から、わかったふりをしない、主観と事実を切り離す、上司に答えを聞かないの3つについて紹介していきます!
仕事ができる人の当たり前の要約

わかったふりをしない
皆さんは、仕事で本当はわかっていないのに、わかったふりをしてしまった経験はないでしょうか?
周りからの評価が下がってしまう、上司から怒られるんじゃないか?といった不安や心配から、わかっていなくても、わからないと言えない人は、多くいると思います。
実際に著者も新人時代に、上司から質問に対して、よく理解していないのに、「そうですね」と相槌のように返答してしまったことがあるそうです。
そして上司から、さらに詳しい質問が飛んできてしまい、うまく回答することができず、上司からこっぴどく叱られる羽目になってしまったと本書で書かれています。
仕事の場において、わからないと正直に言うことは、勇気のいることです。
しかし、仕事においてわからないことを放置することは完全なる悪であると、本書では書かれています。
わからないことを放置したり、相槌のようにそうですねと返答することは、自分の疑問に蓋をしてしまう行為です。
自分の疑問に蓋をしてしまっては、一向にわかるようになりませんし、仕事が進んでいくにつれて、わからないことが増えていってしまいます。
結果的に、周りの同僚やお客様に迷惑をかけてしまうことにつながります。
また、わかったふりをしていることは、最初はうまく誤魔化せても、いずれ周りから見透かされてしまい、「あいつ本当はわかっていないんじゃないか?」と不信感を持たれてしまいます。
信頼がなくなってしまっては、当然重要な仕事を任されなくなってしまいますし、お客様からは契約を切られてしまうかもしれません。
そのため、わからないことがあれば、「わからないので教えてください」と正直に伝えることが大切です。
そして、自分の疑問点を解消し続けていくことで、徐々に仕事に必要な知識が身についていき、周りからも信頼されるようになっていきます。
実際に著者は、上司に指摘されてからは、自分の疑問点を事前にまとめておいて、理解のズレを確認する会議を、上司と毎週行っていたと本書で書かれています。
上司と確認をとることで、自分の疑問点を徹底的に潰すことができ、上司ともコミュニケーションを取りながら仕事を進めることができるようになります。
わかるふりをしないとは、言葉では簡単ですが、意外とできていないことだと思いますが、周りからの信頼を得るためには、とても大切なことですので、ぜひ意識してみてください!
事実と主観を切り離す
皆さんは、仕事の報告をする時に、事実と主観をちゃんと切り離しているでしょうか?
事実とは客観的な根拠です。
そして、仕事ができる人は、相手を説得させ、行動させるためには、論理的に考えて、客観的な根拠を常に追い求めています。
しかし、事実と主観を切り離さずに報告をしてしまうと、相手を謝った行動へ導いてしまう可能性があります。
例えば、上司へお客様との商談の結果を報告する際に、本当はお客様は購入するかどうかを明日までに検討するといっていたのに、「お客様は前向きに検討してくれていて、明日までに決めてくれるそうです!」と回答するとします。
あくまでもお客様は明日までに検討するといっているのであって、前向きかどうか、また明日までに購入を決めてくれるかどうかは、伝える側の希望や願望であり、主観なのです。
そのため、この報告は主観の入った情報であり、事実ではないのです。
またこの報告を受けた上司は、どのような反応をするでしょうか?
おそらく、ほぼ契約は決まったものと考えてしまい、契約に向けての指示を出すと思います。
しかし、お客様は購入するかどうかを明日までに検討するといっていたのであって、前向きに考えてくれていたり、購入を決めてくれるとはいっていないのです。
そのため、本当はあまりいい感想を持っていないかもしれませんし、購入しない可能性も十分にあります。
その場合は、翌日までにするべきフォローや別の提案ができたかもしれませんが、上司に事実を伝えていないが故に、その上司も適切な指示を出すことができなくなってしまうのです。
このように、承認欲求や保身を抑えることができないと、事実を事実として伝えられず、主観の混じった、謝った情報を伝えるようになってしまいます。
それでは当然、相手からは信頼されなくなってしまいます。
だからこそ、事実と主観は切り離すことが大切なのです。
もし主観も伝えておきたい場合は、「事実は〇〇です。主観は〇〇です。」と分けて伝えるようにしましょう。
そうすることで、相手に正しい情報を渡すことができ、信頼を損なうことを防ぐことができたり、相手を正しい行動へと導くことができるようになります。
上司に答えを聞かない
上司に聞いた方が早く仕事が終わるから、上司に答えを聞いた方がいいという考えもあると思います。
確かに、上司に答えを聞いた方が、その仕事はすぐに終わるかもしれません。
しかし、本書では、上司に「どうしたらいいでしょうか?」と答えを聞くことは厳禁であると書かれています。
その理由は、次の3つです。
①相手の時間を奪い、迷惑になる
②思考を放棄している
③ギャップがわからないから成長しない
『仕事ができる人の当たり前』より
まず一つ目の①相手の時間を奪い、迷惑になるですが、相手に「どうしたらいいでしょうか?」と聞いてしまうと、相手は何について答えればいいかを探るために時間が必要になってしまいます。
当然ですが、上司も上司の仕事があります。
私もよく経験があるのですが 、自分が仕事をしている時に、「どうしたらいいか?」と丸投げのような質問が飛んでくると困ってしまいます。
そのため、どうしたらいいでしょうか?と言う時間のかかる質問は、上司にとって迷惑なものになってしまうのです。
続いて2つ目の思考を放棄しているですが、「どうしたらいいでしょうか?」と質問をしてしまうと、相手からは自分の考えがない人だと思われるようになってしまいます。
自分の考えがないということは、価値を生み出すことができない人だと思われるようになってしまい、仕事での評価が下がってしまいます。
最後に3つ目のギャップがわからないから成長しないですが、相手に判断を丸投げしてしまうということは、自分には何が足りないのかを知ることができなくなってしまいます。
自分がこう思うのですがと、自分の考えを先に伝えることで、初めて上司から「ここはこうした方がいい」と、自分の足らない点について指示をもらうことができます。
そうすることで、自分と上司とのギャップを徐々に埋めることができ、成長することができるのです。
確かに私の職場でも、なんでもかんでも「どうしたらいいですか?」と質問をしてくる後輩がいましたら、思うように成長できていません。
「このように対応するべきだと考えたのですが、どうですか?」と聞いてくれる後輩の方が、圧倒的に成長スピードが早く、すぐに昇格していきました。
このように、上司に答えを聞くことは、いっけん仕事を早く終わらせられるため、いいことのように思えるかもしれませんが、実際にはあなたの評価を下げたり、成長を妨げることになります。
その結果、職場では頼られなくなってしまい、必要とされなくなってしまうのです。
そのため、上司に「どうしたらいいですか?」と聞くのではなく、自分の頭でしっかりと考えて、自分の考えを先に伝えるようにしてみてください!
本書では、この記事では紹介しきれていない、仕事ができる人が当たり前にやっていることが、まだまだ書かれています。
そのため、仕事ができる人がやっていることを知りたい、仕事で信頼される人になるためにやるべきことを知りたいという方は、ぜひ本書を読んでみてください!
『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の購入はこちらから!
ではでは。